極アウトプット
「伝える力」で人生が決まる 【書評】
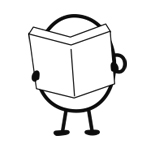
樺沢 紫苑 著(小学館)/ 2021.4.6
著者の樺沢氏は精神科医で、アウトプットのスペシャリストです。メルマガの毎日配信、Youtuber、作家、講演会など他にもめちゃくちゃアウトプットをされています。Youtube「樺チャンネル」では視聴者からの悩み(主にメンタルのこと)に答えているのですが、テキパキと、とても分かりやすく噛み砕いた説明をしてくれています。ちなみに先生がよく言うのは「メンタル疾患の改善に必要なのは『運動、睡眠、朝散歩。』」
インプットとは外からの情報を入れること(受け身)、アウトプットはその情報を整理して外に出すこと(自発的)。割合は3:7でやるのが良いそうです。つまり、アウトプットをたくさんするのが大事。アウトプットをしないことには現実世界が変わらないからです。この本には、アウトプットのやり方がたくさん書いてあります。
主なアウトプットの方法は「話す」「書く」「行動する」。
話す
例えば最近見た面白い本や、マンガや映画のことを友だちに話す。これも簡単なアウトプットです。でもただ面白かった、と言うのではなく、どう言うところが自分は感銘を受けたかとか、キャラクターの性格のここが好き、とかをきちんと言葉にできるようにします。でも実際にやってみるととても難しく、練習が必要ということがわかります。
また、自分のことを話すことによって、相手に自分のことを知ってもらえます。きちんと言葉で伝えなければ相手には理解してもらえないのです。察してもらおう、とは思わずに。
「打ち明ける」というのも大切なことだそうです。気軽に相談するということですね。これは、「問題解決をする」というよりも「気持ちのガス抜き」、という目的の方が大きいそうです。確かに、ずっーと言えずに一人悩んでいたことを誰かに打ち明けると、気持ちがラクになるということがよくあります。しかも、言ってみたら人からすればなんてことはなかった、ということが多かったりして。どうして楽になるかというと、打ち明けることによって「問題点が整理される」からだそうです。誰かに話すことで頭の中の考え事の一つが外に出されると、そのぶん脳の中に余裕ができて、パニクっていた状態から抜けられるのだそうです。
「ありがとう」を言おう。
わたしは、家族、友人、お店の店員さんなど周りの人に積極的にありがとうと言うようにしています。余談ですがいつからそうしているかいうと、かつて親しい人が突然亡くなってしまって、本当はいろいろお礼を言いたかったのにもう言えなくなってしまった。ということがあったからです。後悔しないように、言える時にすぐに言っておこうと思って。
さて本題に戻りますが、ありがとうは、言われた人も、言った人にもよいい影響がある言葉だそうです。お互いの脳内に幸福物質が出て、癒されたり免疫力が高まるのだそうです。すごい言葉 !
謝ることも大切なアウトプットだそうです。「ごめんなさい」はプライドのせいで言いにくいこともあるかもありません。わたしも素直に謝れないことがよくあります。特に夫に対してとか(どんだけ〜)
しかし謝ることは、自分自身の行いに対するフィードバック(見直し・方向修正)になるので、とても有益なのだそう。そんなこと考えたこともなかった。
争いごとに関してどちらかが100%悪いということはありません。なのに、「ムカつく〜!」と言っているだけでは相手がなぜ怒ったのかわからないし、相手の立場からしたらあちらの言い分もあるわけですから、感情と事実を切り分けて考える、事実確認をしてなぜ相手が怒ったのかを分析、今後の策を考える。これで少し成長できます。
それに、きちんと謝れる人は人間の器が大きいと感じますよね。相手からの印象もよくなります。
書く
書くことは話すことよりも記憶に残り自己成長を促し、学習能力も高まるのだそうです。わたしもやり始めたのでしみじみ感じるのですが、自分の頭の中にある、もやもやと考えていることを言語化するというのはとても難しいです。でも書けば書くほど伸びるということなので続けていこうと思います。
(また後日紹介したいと思いますが、「ゼロ秒思考(赤羽雄二 著)」を読んでからほぼ毎日メモ書きをしています。)
簡単な方法で、日記を書くというのも紹介されてたので始めました。これにより「自己洞察力」が鍛えられるとのことです。加えて3行ポジティブ日記も始めました。今日あった出来事で嬉しかったこと、楽しかったことなど思い出して3つ書くというものです。はじめは正直、そんなに思いつきません。ですが、むりやり見つけ出します。どんな小さなことでもいいのです。日常の中に幸せなこと、楽しいことってたくさんあるのですよね。それに気づくための練習です。
楽しいことを見つける能力が高まるとドーパミン(やる気をアップさせる成分)が分泌されやすくなる→集中力や記憶力が高まるのだそうです。これは寝る15分前にやることに意味があります。睡眠前の15分は記憶のゴールデンタイムと呼ばれ、この時間にポジティブなことを思い浮かべるとそれが記憶に残りやすくなるというのです。これでポジティブ思考が増していき、楽しい毎日が送れるようになるということです。わたしは今、実行中です。
そして、読書感想文を書くのも自己成長につながるとても良いアウトプットなのだそうです。(この、わたしのやっている書評という名の読書感想文もそう信じて続けていきます!)
感想を書くことを前提に本を読むので、多くの情報を読み取れるようになるとのこと。さらに人に伝える、ということをすれば自分が理解しないとできないことなので、きちんと読もうと思うのですよね。
わたしは読んだ本の自分の記録のためにも、この書評を書いています。
行動する
【ここが一番重要】どんなことでも、せっかく知識を得ても実際に行動しなければ何も変わりません。
インフルエンサーの人たちがよく言っていますが、「こうすればいいとアドバイスをしても、実行する人はほとんどいない。」のだそうです。
この本によると、人にはコンフォートゾーン(快適領域)があって、それを出ることを恐れるように、脳にプログラミングされているそうです。
でもそこを抜け出してチャレンジしないことには、成長はない。さてどうしたら良いか。それは、「ちょっと頑張ればできることにチャレンジする。」ことなのだそうです。これなら出来そうではないですか。
樺沢先生によると、多くの人は目標が高すぎるのですって。なんかわかるんだけどね。。。
大きな目標を細かく分割して、ちょっと出来そうな小さなことに分けていって、それを一つ一つクリアしていけば良い。
100%できそうなくらいハードルを下げるのです。
さらにちょっと頑張ればできる問題に直面した時に、脳内ではドーパミンが大量に分泌されるので、集中力、記憶力、学習機能が高まるのでいいことづくめです。
わたしもついあれこれと出来もしないことを目標にしがちで、最近は「欲張らない」を座右の銘にしています。笑。
「0か100か思考」これもよく自分がやりがちなのですが、物事には必ずグレーゾーンや中間地点があるのに、白か黒かで考えてしまいます。何かをやった時に、成功なら100、失敗なら0としてしまうのですが、大体うまくいったとなれば70くらいでいいし、まあちょっとダメだったかなと思っても20とか30くらいはあるはず。きちんと数値化することにより、現状を把握することができます。少しでも前進できたら成功です。
そして、行動とセットでするべきなのがフィードバックだそうです。
「フィードバックは失敗を経験値に変える作業」。何かにチャレンジして失敗したとします。それが、なぜうまくいかなかったのか。原因を分析してこれから改善すべきことは何かを書き出すことができれば、それはデータになり、小さな情報の一つとなる。失敗ではなくエラー(トライ&エラー)。実験していると思えばその結果が出ただけのことですよね。そして、エラーによってストレスを受け流すしなやかさ(レジリエンス)も得られるそうです。
成功者と言われる人たちは、成功したことだけが見えるのでわかりにくいですが、見えないところにはたくさんの失敗(挑戦)があるといいます。とにかく、たくさん打席に立つのが大切なのです。と色々な方が言っていますがその通りですね。あとは案ずるより産むが易しってこともあるしね。ちょっとだけ勇気を出してみよう。
いかにアプトプットが大切だと言うことがわかります。楽しみながら自己表現をする。アウトプットが上手にできるようになるとたくさんのいいことがあります。コミュニケーション、仕事、勉強などたくさんのことに応用できます。やらない理由がないです。
この文章で、少しでもこの魅力が伝えたれたらいいと思っています。
ほかにもたくさん実践できることが書いてありますので、気になった方は是非読んでみてください。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d2cbee1.d1029144.1d2cbee2.ad2ff642/?me_id=1213310&item_id=20297450&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2835%2F9784092272835.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
