反応しない練習(前編)【書評】
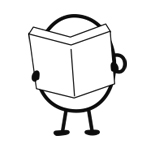
草薙龍瞬(くさなぎりゅうしゅん)著(KADOKAWA)/ 2015.7.29発行
これは、わたしの大好きなイケメン企業家の「マコなり社長」オススメの本です。
ブッダの合理的な考え方を用いて様々な「悩みを消す」、
そのための思考方法を書いています。
ブッダとは「正しい理解を極めた人」だそうです。
正しい、というのは自分の解釈での見方ではなく、ニュートラルに、客観的に物事を見すえるという意味です。
とてもたくさんあるのですが、簡単なことから実践してみます。
基本になるのは、「ムダな反応をしない」こと。
実にシンプルです。だから難しい。
どの悩みも「心の反応から始まっている」のだそうです。
「悩みをなくそうとしない。理解する。」
まず、人生において、悩み・問題はつきもの。という現実を受け入れる。
そして、そこからそれによって苦しまないように練習していくのです。
その方法は大きく分けて2つ。
1.心の反応を見る
2.合理的に考える
1.心の反応を見る
第1章 反応する前に「まず、理解する」
こうすることにより、ざわついた心が静かになるそうです。
現実を受け入れる、のではなく「あると理解する」
よく悩みは紙に書くと消えるといいます。
漠然としたことを頭の中で悶々とさせているより、
実際に書くことで「悩みがあるということ」、「何を悩んでいるのか」をはっきりできるのでしょう。
何を悩んでいるのか分かれば、そこから、ではどうすればいいかと考えて前へ進められます。
その「悩み」には原因があって、仏教では執着から来るものとされているのだそうです。
そしてさらにその前に、悩みを作り出すもの「心の反応」があるのだそうです。
まず執着となる人間の欲求(求める心)7つとは。
①生存欲 ②睡眠欲 ③食欲 ④性欲 ⑤怠惰欲 ⑥感楽欲 ⑦承認欲
この中でも「承認欲」は人間だけが持つもので、特に現代のわたしたちに関係が深いのだそうです。
これらの欲を、まずは「心とはそういうもの」そして、「心は求め続けるもの」と理解しておくことが必要です。
【理解するための練習実践 1 】
くり返し言葉に出し、客観的に理解するように努める。
例)「この不満は、承認欲の不満だ」など
ちなみに承認欲は、人の目が気になる・嫉妬心・比較して優劣や勝負けにこだわる心理などの原因になります。
この承認欲を「ある」と理解することが、正しい心がけだそうです。
【理解するための練習実践 2】
「心の状態を見る」これを習慣にするといいそうです。
①ココロの状態を「言葉で確認」する
心の状態、体の動作を客観的に言葉で確かめる習慣を身につける
例)「疲れと感じているな」「イライラしているな」 など
日常の動作でも同じように。「今掃除をしている」「今歩いている」など
②感覚を意識する
日頃から動かしている体の感覚をよく意識して感じとる… マインドフルネスですね。
③(①をもう少しざっくりを分けて)頭の中を分類する
心の状態をいくつかの種類に分けて理解する方法
[ちなみに下記3つは三大煩悩と呼ばれるそうです]
1 貪欲(とんよく)(求めすぎている状態)
2 怒り(あまり根拠のないもので、悲しみも怒りの一つである。)
3 妄想(これは人間のNo.1に輝く煩悩だそうです。)
妄想は楽しいことに使えればいいですが…
この「妄想」を解くには「リセット」することが必要です。
その方法は、
妄想に気付いたら「今、妄想している」と言葉で確認すること。
そして妄想は心の内側にあるものなので、心の外側にある体の感覚を意識するのがベスト。
瞑想(めいそう・マインドフルネス)はまさにそうですよね。
自分の呼吸に集中したり、鼻から入る息を感じたり。
歩行瞑想は、足の裏の感覚に集中しながら歩行するというもので、メンタリストDaiGoさんもやっているそうです。
2.合理的に考える
第2章 余計なことを判断しない。どんなときも、自分を否定しない
第3章 不満やストレスといった「マイナスの感情で苦しまない」
第4章 他人の視線を気にせずに、自分らしく生きる
第5章 勝ち負けや優劣にこだわってしまう性格をもうやめる
最終章 心から納得のいく人生を、ここから目指す
さて、第2章「良し悪しを判断しない」です。
人が悩む理由の一つは「判断しすぎる心」決めつけ・思い込みなどです。
これは、不満・憂鬱・心配事などを作り出すのだそうです。
「いい悪い・好き嫌い」などついやってしまいますね。なぜか。
判断する心には、わかった気になれる気持ちよさと、自分は正しいと思える快楽があるのだそうです。だからやめられない。止まらない。
判断とは、妄想にすぎない。それに気づくこと。
【判断しないための練習実践 1】
1 判断に気づくこと
「失敗したかも」「あの人苦手、嫌い」という思いがよぎった時に「あ、判断した」と気づくこと。
「良い人だな」というのも判断です。
2 自分は自分と考える
「世間にはこういう人もいるかもしれないが、わたしはこうしよう」と他人と自分との間にきっちりと線をひくこと。
3 いっそのこと「素直になる」
【判断しないための練習実践 2】
●どんなときも自分を否定しないこと
1 一歩、一歩と外を歩く
何ヶ月でも、何年でも自分を否定する判断が消えてなくなるまで散歩し続けてみる。
じっくりと肚(はら)をすえて、心の自由を取り戻すまで歩いてみる。
ネガティブな判断が心に湧いてきたら「ゲームオーバー」だと考える。
2 広い世界を見渡す
自分は狭い世界で一人思い込み、勘違いをしていたのかもしれないと気づくこと。
3 「わたしはわたしを肯定する」と自分に語りかける
シンプルな言葉で、判断を停止させる。
自分を否定しないのは、それに合理性がないからです。
理由は
1 その判断が苦しみを生んでいる
2 その判断は妄想に過ぎない
から。要するにムダなことですね。
それよりは、今何をすべきか。なにができるか(行動する)。
この瞬間だけを考えるのみ。断然合理的。
●本物の自信とは
自信があるかないかというのも判断です。つまり妄想です。
なので「自信が欲しい」というのは不合理なことです。
自信なんて考えなくて良くて、それよりも今しておくべきことをする。
わたしは自分でいうのもなんですが、自信がないタイプです。
この本によればそういう妄想をしているのです。
なので、自信をつけるためにチマチマと努力をしていけるのですが、
それがちょっと間違えた思考だといいます。
妄想の上に、違う妄想を重ねている、思考のミスだそうです。
そもそも「自分はまだまだ」という思考の始まりが「ネガティブな妄想」で、
そこから降りないと「自分はできる」という思いを持てずにずっと「自信が欲しい」という
思いに駆られるのだそうです。
ただ今すべきこと、今できることをやっていく、やってみることの方が大切で「自信が欲しい」とは考えないこと。
やってみる。
とりあえず体験を積むだけで良い。
できるかできないかという結果に執着しない。
これって、しなやかマインドセットの考え方に似てるなぁ。。。
少し長くなってきたので、次回に続きます。
わたしが大好きなイケメンFlutistのエマニュエル・パユ氏が、
本番での心構えについての講義の動画で、こう言っています。
「『うまくいかなかったらどうしよう。』という気持ちが出てきても、それに答えてはいけない。
なぜなら、質問が間違えているからだ。」
そもそも、今回2度も大好きイケメンとか言っている時点で反応しちゃってるな…
反応しない練習(後編)【書評】
https://eggsblog.com/2021/03/01/hannnou2/
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d2cbee1.d1029144.1d2cbee2.ad2ff642/?me_id=1213310&item_id=17518526&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0400%2F9784041030400.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
