なぜ、あなたの仕事は終わらないのか
スピーードは最強の武器である【書評】
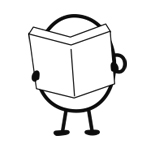
中島 聡 著(文響社)/ 2016.6.7
1960年 北海道生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科修了
この本を読むまで、わたしはまだ生まれていませんでした(もちろん比喩です)。
中島氏は、 ざっくり言うとビル・ゲイツと一緒に仕事をして、Windows95、今ではお馴染み右クリック、ダブルクリック、ドロップアンドドラッグを作ったすごい人。今まで存じ上げなくて申し訳ありませんでしたm__m
前書きには時間術の本ですとありますが、ノウハウのほか歴史、仕事術、教訓など盛りだくさんの内容です。これはもう教科書にして、すべての人が読むべきと思います。
今、スマホやインターネットの出現でここ数年で特に価値観が急激に変わり便利になりました。ようやく2年くらい前からわたしもプログラミングを少しなめて(かじるまでもいかない)みました(まだまだ勉強中)。いい時代になって「今の学生はいいなー。」などとよく思っているのですが、戯言ですね。
著者は約30年も前からプログラマーとして数々の偉業を成し遂げています。
大学時代にはソフトウェアを開発し、大学院卒業後にNTTに入所しますが、企業の体質に疑問を感じて退社、マイクロソフト社の日本法人に転職します。
高校2年生の時にパソコンを買ってもらい(約44年前)、そこからがっつりプログラミングにはまります。どんなに大変でも走り続け、「自分が幸せになれる行動しないと、人は幸せにはなれない。」ということに気づいたのだそうです。
内容が濃すぎてキリがないので、特に刺さったところを書きたいと思います。
時間は皆平等
これだけの偉業を目にすると、とても自分には無理なことだと思ってしまいますが、著者は時間を制することで誰でも生み出せると言っても過言ではない、とおっしゃっています。
たしかに、わたしが敬愛する起業家の方々も皆、時間をいかに効率よく使うのが大切かを言っています。
著者もビル・ゲイツさんを間近で見ていてそれを強く感じたそうです。例えば社員の説明を聞くための専門の社員がいたり(説明の下手な社員から聞く時間がムダなので、代わりにあらかじめ聞いておいて要点をまとめてもらうため)、プレゼンの時間は質疑応答のみで30分以内に終わらせるなど。意思決定も光速で。
あとは、認知資源(決断や意思決定をする時に減少する気力みたいなもの)を減らさないように、偉人は毎日決まった服を着るというのも有名な話ですね。わたしもそこは真似しています。ほとんどユニクロとallbirdsです。
また、仕事の締め切りを守ることを重視していたそうです。
当たり前のようなことですが、それを当たり前にできるか。それが重要ですね。
ロケットスタート術
さて。中島氏が提唱するこの方法。仕事をする集中力を発揮する割合を2:8で行うとしています。例えば納期が10日としたら、最初の2日はスタートダッシュを決めてそこでほとんどを仕上げる。なんでも、ドラゴンボールの悟空が使う「界王拳」と言うのをイメージするそうです(わたしはカメハメ波しか知らないTT)。残りの8は余力で流す。流すと言っても適当にやるのではなくて、余裕を持って仕事をすると言う意味です。この心理的な余裕を「スラック」と言うそうですが、これがとても重要とのこと。確かに、焦ってやっていい結果が出ることってまずないですよね。そして、たとえ2日で終わっても、そこで提出しないことだそうです。早く出してしまうと次々に仕事がきて、結局余裕がなくなってしまうからだそうです。いい仕事をするために、そこまで考えて調整しているのです。
また、多くの人はラストスパート志向にあると言います。それが悪の根源なのだそうです。その仕事がどのくらいで出来るのか正しく見積もりができずに、余裕と思っているうちにギリギリになって焦って仕事を終わらせようとする。それで間に合わなかったら最悪です。
スタートダッシュで取り組んでみるとどのくらいで終わるか、納期に間に合うかどうかがわかるので早いうちに納期の調整ができるし、大体出来上がっていればあとは余裕を持って取り組めます。
氏がこの方法を思いついたのは、小学生の夏休みに海に誘われたので行きたかったのに、宿題が終わっていなかったので家の人に許可をもらえず行けなかったのが悔しかったからだそうです。
わたしも、時間に余裕があるとついだらだらしてしまって、結局何もしないで最後になってあわてる。ありがちです。これからはそれを確実に変えていこうと誓ったのでした。
すべての仕事は、必ずやり直しになる
これは、初めから完璧を求めずにやり直しがあると認識して、プロトタイプ(試作品)を作りましょうということです。どうせやり直しになるなら細かいことは気にせず全体像を作ってみる。これは何にでも当てはめることが出来ると思います。例えばこの書評を書くのにも、大枠で何を書くかを決めておいて、そこから細部を書いたり、直したりする方が早く書けます。
Windows95が日本で販売された時、店に人の行列ができている映像をTVで見たのを今でもなんとなく覚えていますが、当時Windows95には約3500個のバグ(不具合)が残っていたのだそうです。それだけ聞くとかなり驚きます。ただ、一般のユーザーが使用するにあたっては困らないものだったので、バグを修正していて販売が遅れるよりも、お客さんにとっていいものを素早く提供する方が大事だったのだそうです。アプリケーションもよくアップデートがありますが、あれもバグの修正なんだそうです。なんでもそうですが、100%の製品を作るのって、まず不可能ですよね。
ダブルクリックは日本語ならではの発想だった?
プログラミングの中でオブジェクト指向というものが出てきます。
これがなかなか理解するのに難解なのですが、Windowsで文書ファイルをダブルクリックしたら自動的に編集するとなり、音楽ファイルなら再生するというコマンドが選択されます。このように何らかの対象(オブジェクト)を先に選択したら、次に動作を指定することをオブジェクト指向というのだそうです。
これが、日本人的な会話の作法に似ていると言います。例えば車の助手席にいて運転手に道案内をする時、「そこを右ね。」といえば、運転手は右に曲がります。「右がなんだっていうんだ?」とはなりません。右と言った時点で、そちらに曲がるということは決まっています。
著者がこれ(ダブルクリック)を思いついたのが日本語話者だったからかもしれないのです。すごく深い話ですよね〜。
もし、今の自分を変えたかったら
この後、さっそくポチってこの本を読んでみてください。
とても分かりやすく、読みやすいです。
そして、一つでもこの本にかいてあることを実践してみてください。
「一度しかない人生、思いっきり楽しもうぜ。」だそうですよ!
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d2cbee1.d1029144.1d2cbee2.ad2ff642/?me_id=1213310&item_id=18036694&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3413%2F9784905073413.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
